分譲住宅ブランドTIARA
住まいへの憧れとこだわりを、もっと多くのご家庭へ。
飯田グループホールディングスでは、土地の仕入れから設計、施工、アフターサービスまでをグループ内で行う一貫システムにより、良い家をお求めやすい価格でお客様にお届けしています。
ティーアラウンドは、そんな家づくりの特徴に、独自のデザイン技術をプラス。多くのご家庭が、時代のニーズに合わせたスタイリッシュな住まいでの暮らしを実現できるよう、性能・価格・デザインのバランスが整った新築住宅「TIARA」を提供しています。

TIARAブランドとは
安心と安全
「住宅性能評価 7 項目最高等級」を取得。地震や劣化に強い構造体、夏涼しく、冬暖かい断熱性など、住まいの安心と安全を考慮した高性能住宅。
デザイン性
住まうことが楽しくなる。家族に永く愛される、飽きのこないスタイルを追求し、資産価値向上にもつながるスタイリッシュな住まい。
価格のバランス
飯田グループホールディングスのスケールメリットを活かし、お求めやすい価格を実現。性能・デザインに優れた住まいを、多くのご家族へ。
TIARA
ブランドの由来
当社の家づくりのコンセプトである『笑顔のすまいをプロデュース』『最高の生活提案』の
想いに準じたブランドネームです。
ネーミング
コンセプト
「 この物語は、理想を叶える
特別な未来への継承。」
ティーアラウンドは、
お客様の理想に寄り添い、
子や孫、未来へと継承される
住まいを目指しています。
T = Tale 物語
I = Ideal 理想の
A = Answer 叶える、応じる
R = Regalia 特別なもの(王位継承・王権の標章)
A = Around 続く、繋がる、継承
センスの良いデザイン住宅
快適な住まいに
洗練された美しさを。
経験・実績ともに豊富な建築デザイナーが、一邸ごとにコンセプト立案から間取りプランニングまでを担当。重厚な質感の個性が際立つ外観、モダンでスタイリッシュ、飽きのこない心地よさを表現した内観ともに、洗練された美しさを追求しています。
詳しく見る
住宅性能・工法
住宅性能評価7項目で
最高等級を取得。
「TIARA」シリーズは、全棟で住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)をダブル取得。住宅性能評価7項目最高等級が証明する、永く、安心して暮らせる住まいを提供するために、住宅性能や工法に関する厳しい品質管理を徹底しています。
詳しく見る
オーナーサポート
ご入居後も安心の
オーナーサポート。
お引渡し後、5年ごとに無償診断を受け、必要なメンテナンス工事を実施していくことで、保証を最長35年間延長可能。充実したアフターサービスも整備して、住まいに関するお客様のお困りごとにも迅速に対応します。
詳しく見る


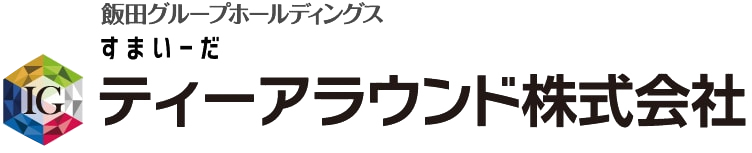
 〉分譲住宅ブランド TIARAについて
〉分譲住宅ブランド TIARAについて 〉センスの良いデザイン住宅
〉センスの良いデザイン住宅 〉家族が安心の住宅性能・工法
〉家族が安心の住宅性能・工法 〉購入後も安心のオーナーサポート
〉購入後も安心のオーナーサポート 〉施工例
〉施工例 〉建築シミュレーション
〉建築シミュレーション 〉購入後のお客様 一覧
〉購入後のお客様 一覧 〉購入直後(6ヶ月以内)の方
〉購入直後(6ヶ月以内)の方 〉住んでからのサポート
〉住んでからのサポート 〉代表メッセージ
〉代表メッセージ 〉経営理念
〉経営理念 〉会社概要
〉会社概要 〉グループ会社
〉グループ会社 〉SDGs
〉SDGs 〉ビジネスパートナー募集
〉ビジネスパートナー募集 〉採用情報 一覧
〉採用情報 一覧 〉会社を知る
〉会社を知る 〉充実の福利厚生
〉充実の福利厚生 〉仕事を知る(インタビュー01)
〉仕事を知る(インタビュー01) 〉仕事を知る(インタビュー02)
〉仕事を知る(インタビュー02) 〉仕事を知る(インタビュー03)
〉仕事を知る(インタビュー03) 〉募集要項・採用エントリー
〉募集要項・採用エントリー
 販売中の物件
販売中の物件






